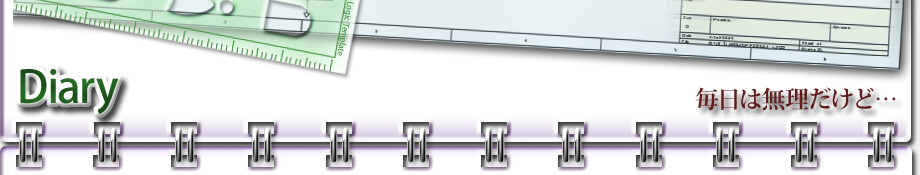-過去ログは古い順に並んでいます-
2014年 11月 2日(日)21.5℃(午前 4時51分)
ついに11月突入
昨夜はガネーシャのおごりで、牛を焼いてきました。とってもおいしくいただき大満足です。また連れてってください。牛焼きへ……。
と言っても、もうおっさんですので、大した量は食べられませんが……。

牛焼きです……
話しを変えて──。
このところ、連休に入ると雨が続く関西ですが……。
11月の連休も雨で始まりました。
せめてもの、清々しい写真を。

先週の日曜日……とある公園です
絵に描いたような秋晴れの素晴らしい一日でした。
たまにはワタシもこういうところへ行きます。
たま~~~にですが、PCから離れる時があるのです。なぜなら、この連休をべったりPC日和にするためです。
何をするか、まずは第一弾。三線USARTです。
やっとデジタルな話しになりそうです。ここんとこ、どこかのデザインソフトメーカーの片棒ばかりを担がされている、いや自分から担いでいるのですが……。と言うより悪いことはしてませんので。
──これから紹介するようなことをコツコツするのが、ワタシの真の姿です。
その割にはUSARTですか?
USBやBluetoothの時代に、えらく古臭いとお思いでしょうが、ランクの低い(すみません)──お手ごろなランクのPICに内蔵されている通信機能ですので、これを使わなくて何を使うと言うのでしょう。なにしろUSBプロトコルの入っているPICは高いし、フラットパッケージだし(DIPもあるのですか? ワタシは知りません)。
Bluetoothだと無線ユニットが必要で、安価なRBT-001(ROBOTECH社のモジュール)がありますが、結局これもUARTでPICと接続することになります。
だからUSARTをもっとお手軽に、モジュールどうしを三本の線で接続して通信し合おうというのが、今日のこれです。
シリアル通信だからもともと接続コードは、TX、RX、GND の3本じゃないか、とお思いでしょうが、相手のモジュールに電源供給までして3本で済まそうというものです。ちなみにUSB 2.0までは4線ですよ(ミニマイクロUSBは5線ですし……)
なんだか大げさなことを書いていますが、単純に受信、送信ラインを一本にして、残りをGNDと、電源線にしているだです。でも意外とこの通信線を一歩にまとめるというが、便利いいんですよ。
なぜかというと、自分の吐き出した(送信した)データが正しく経路を伝わっているかというモニターができるので、ジャミングが起きて通信データが潰されたとか、経路が電源とショートしてデータが潰れた、とかが判断できます。
回路はこれ。

【3線 USART 回路図】
TX、RX 端子はPICのTX、RX ポートに接続します。受信バッファーにデータがそろったら、割り込みが掛かるように設定して使うのがいいかと思います。
送信部分はメイン処理の中で行い、データを送信バッファーに送れば、あとはPICがやってくれますし、受信したシリアルデータを通常の1バイトデータに変換して受信バッファーに放り込む作業もPICがやってくれますので、プログラムは受信完了の割り込みを待つだけです。
つまり送信バッファーに1バイトデータを放り込んだ後、すぐに割り込みが掛かります。自分が送ったデータを受信しますので、送信データと受信データを比較して同じなら、相手に無事に届いているだろうと判断してもいいでしょうね。
1バイトのデータをやり取りするなら、単純でいいのですが、数バイト単位になると受信処理に工夫が必要で、1バイトごとに、どこかのテーブルへ並べていくのが一般的だと思います。全部受信ができたら、自前の受信完了フラグを立てて、メイン処理に知らせます。
数バイト送信もテーブルから順番に読み出して、送信バッファーが空になるたびに送り続けるという処理の繰り返し後、受信完了フラグが立つのを待って、データの比較をするということになります。
数バイト単位の受信は、途中でデータが潰されたり、途絶えたりすると、残りの受信を待ち続けてしまったり、途切れた先のデタラメなデータから受信を再開したりすることがあります。潰れたデータ列を受信した時はチェックサムで弾くことができますが、しばらく途絶えた時などはデータ終了がわからずハングアップしたりしますので、受信間隔に隙間が開いたらエラーとして弾いて再送を要求するのがいいとお思います。
古典的な方法ですが、9600bpsで8バイト程度の通信なら感覚的には瞬間で、意外と重宝しております。
2014年 11月 9日(日)20.5℃(午後 4時31分)
日本語入力環境、座礁する
Win8.1を載せているPCには日本語編集環境がほとんどなく、ちょっと悩んでいます。
このページや、おバカな話(SF大好き)に書き出す文章は、テキストエディッタか、WORDを使っています。ところが、この二つのソフトともにWin8.1にインストールすると、PCが固まります。つまりWin8.1に対応していないのです。
Win7ではテキストエディッタもワードも健在ですが、先日、Microsoftの日本語入力ソフト(MS-IMEとか言われるモノです)、Windowsなら必ずくっついて来る、画面の右上か下に常駐していて、『漢字』キーを押すと『あ・般』とか表示されるやつです。
あれをMS-IME2010にバージョンアップしたのですが、その途端、WORDが縦書きしかできなくなってしまったのです。
横書きにすると、十数行でフリーズします。縦書きで入力するといくらでもできます。
まぁ、おバカなページは縦書きで書いていますので、問題ないのですが、西宮文学全集は横書きです。
今日、久しぶりに締切に間に合うペースで書いていたのですが、にっちもさっちもいかなくなって、サジを投げました。1ページも進まないのです。数行書いては固まり、一度セーブするとまた数行書ける、という始末で、もう怒り狂いました。
最新のWORD2014を購入して、Win8.1に移行しようと、ネットを彷徨ってみると、辛口批評ばかりでてきます。そのクレームのほとんどはインストール関係と突然のエラー関係でしたが、これはなんでもそうじゃないの? と、ついこの間までWin8.1で散々な目にあってきたワタシですので、ここは大目に見て。
でもここにきて『一太郎』が浮上。WORDと比較すると、MS-IMEに対抗するATOKの性能が素晴らしくいいなどと書かれているのが多く。急激に使ってみたくなりました。
MS-IMEでも不満はないのですが、あまりにATOKを絶賛する書き込みが目につくと、ちょっとなびいてしまいますよね。
だからWin8.1は『一太郎』にしようかと迷っている今日この頃です。
ところで、MS-IME2009にダウングレードってできるのでしょうか?
このままではWin7でもWORDが使えなくなります。
やれやれだぜぇ。。。。。 ┐( ̄ヘ ̄)┌
2014年 11月20日(木)13.5℃(午前 7時20分)
ひと息すると腐るのです
支離滅裂・意味不明の物語もようやく収束し、ちょっと一服するか………なんてやっていたら、体の下のほうから腐海の侵食が始まってくる気配を感じて───。
これはワタシの病気「止まると死ぬのだ病」を書き表そうとしてみましたが、これではまるでマジで黒い病みたいなイメージになり、
「アイツ大丈夫か?」
と思われるのもなんですので、ちょっと視点を変えて書かせてもらいますと──。
魅惑の泉が次々と湧いてきて、じっとしていられない──ということで、どうでしょうか?
これが、小学校の通信簿の連絡欄に「落ち着きがありません」と6年間書き綴られていた結果です。
やりたいことが目白押しで………、次は順番からいくと、After Effects(アドビ社製)になります。
これは、最近ここでちょくちょく出てくるプレミア(アドビ社製)という動画編集ソフトと連携して使用するアプリです。
(連携する、しないは個人の自由ですが……)
まず、プレミアというアプリは、たんにムービーの編集だけにあらず、それにFlashの機能を合体させたようなイメージを受け、これまでFlash一本だった、ワタシの目からウロコ的な物でして。After EffectsはFlash+Photoshopみたいな感じで、二つそろったら、鬼に金棒、状態です。
こういうものが大好き人間には蠱惑的(嵌まると体を蝕まれるという意味では)で堪りませんねぇ。ネズミにチーズ、猫に鰹節ぶっかけゴハンっす。
ちなみに、ネズミはチーズが嫌いだそうです。それから鰹節ぶっかけ猫ご飯は、いまや人間しか食べないそうです。
で、こいうアプリは、この記事を書いているWin7ではビット数が足りませんので動けず、我が家のマジ○ガーゼットくんの出番ですが、まだ未熟なWin8.1搭載のため、しょっちゅう立ち往生しています。
昨夜も、"更新しています。PCをこのままにしてお待ちください" のまま、4時間止まったまま。いくらなんでもおかしいだろうと、強制終了。電源ボタンの長押しをしましたが、画面は変わらず。
「んにゃろ~」と心で叫びつつ。夜ですので、声には出しませんが……、 気付くとマシンは何のキーも利かなくなっており、フリーズさんです。
このまま部屋の照明に使うには暗すぎるため、やむなく、
「またかよ~。Win8.1め~」と電源コンセントごと引っこ抜き、再起動。
さっきは "更新、1個中1個" と表示していたくせに、今度は "更新、26個中26個" に変わっていました。
「なんじゃ?」
と首をひねっているまに終了しましたので、一件落着ですが………。
仕事で使うマシンと、検証用マシンを併用するとこういう不便なことになるという実例ですね。
製作物を検証するにはxp、win7、win8.1、iMacなどのマシンが必要になるためです。
ホームページ物になると、さらにiEも8~11、fireFox、Sfari、Google、などでも検証します。
おーじょうしまっせ
2014年 11月22日(土)16.0℃(午前 7時12分)
連休ですが……なにか?
本日、西宮文学全集11月号更新しました。
すっかり月後半が更新日になってしまいました………そうしてしまった張本人はワタシです。すみません。
昨日の前半は(後半は秋の山に行きました)、アドビシステムズのAfter Effects(以降AEと書きます)をさっそくいじり倒してみました。
以前、アドビシステムズのPhotoshopとFlashを足したようなものと書きましたが、これはあくまでも個人の感想で少し訂正させていただくと、アクティブPhotoshopという感じのほうが近いかもしれません。
ここからは自分の覚書として書き綴り、またAEを学んでいる方の何かの参考になるのでしたら、どうぞご自由に閲覧していってください。
After Effects(アクティブPhotoshop ←勝手にそう呼んでいます)の参考例として、
この例ではPhotoshopでおなじみの、レイヤースタイルのベベルとエンボスを施したテキストをFlashの簡易3Dのように見せて、ついでに、これまたPhotoshopでお馴染みのレンズフレアーを施しています。
Photoshopの場合は動きませんが、AEではそれをFlashのように動かすことができます。
ここからは覚書です。
テキストのベベルはテキストレイヤーに書かれた文字を選択した状態で、レイヤー → 新規 → レイヤースタイル → ベベルとエンボスとやって、タイムライン左で各種パラメーターを変更します。
レンズフレアーは、まずレイヤー → 新規 → 調整レイヤーを作り、それを選択した状態で、エフェクト → 描画 → レンズフレアーとやります。
光の加減や、レンズ設定などもタイムライン左横の調整ウインドウで行います。
ただし、レンズフレアーは動かしますので変化点のタイム位置でキーフレームを作ってパレメーターをいじります。
次に簡易3D設定です。
レイヤー → 新規 → カメラ
レイヤー → 新規 → ヌルオブジェクト
と二つ作っておき、ヌルオブジェクトの下にカメラをレイヤーを置きます。そしてタイムライン左のウィンドウでヌルオブジェクトをカメラの親として指定します。
こうしてヌルオブジェクトのほうのx、y、z軸を調整して立体的に動かし、カメラは触らないようにしています。
最初カメラを動かしていたのですが、えらい目に遭いました。支離滅裂、摩訶不思議な世界に迷い込み、元に戻れなくなります。初心者のうちはこれがお手軽そうです。
それと動かすテキストレイヤーなども含めてすべてを3Dレイヤーに変更します。
そうしないと3Dの動きをしてくれません。
方法はレイヤを選択しておき、レイヤー → 3Dレイヤーを選択です。
あとはヌルオブジェクトのタイムラインの任意の時間位置にキーフレームを打って、座標を動かすだけです。
つまり、テキストの配置を奥行感を持って設定しているだけで、全く動かしていません。動かしているのはカメラだけです。
奥行き感を持ってテキストの位置を見るには、2画面表示に切り替えて、左側をトップビューにしています。ビューは、フロントや右からとかいろいろあります。
こうするとテキストを真上から見た状態に(テキストのある位置がラインになっています)なり、どれだけ奥へ引っ込んでいるか(z軸)を調整できます。
完成動画の書き出しは、ファイル → 書き出し → レンダキューに追加、をして、mp4を書き出すなら、
出力モジュールの項目「ロスレス圧縮」をクリック、H.264 選択、形式オプションで、ビットレートを調整ができます。
これで、Flashではできなかった滑らかな動きと光の効果が得られます。ただし欠点は、ファイルサイズが大きいこと。
今回のはなるべく小さくしたかったので、約4秒で抑えて、ターゲットビットレート1.5Mbps、最大ビットレート1.5Mbpsにして697KBでした。
スマホ相手にするのなら4Mbpsは欲しいところですが、まぁサンプルと言うことで……それにしてもFlashの3~4倍の大きさはありますからね。
悩んだのがスクラブ再生です。
タイムラインのインジケーターをFlashみたいにマウスドラッグで左右に動かすと、それに合わせて時間的に前後に移動して、画像が動きますが、なぜかワタシのAEは動いてくれませんでした。ネットを彷徨っても普通にスクラブ再生をしているようです。
またもやWin8.1の呪いかと思っていましたが、よく見るとタイムラインインジケータの矢印が、うちのは青いのです。ネット上のはオレンジ色をしています。どこかに設定でもあるのではないかと調べましたが、見つからず。で結局。altキーを押しながらマウスをドラッグするとスクラブ再生してくれましたので、まぁいいか、とこだわるのをやめました。
PCに関して、小さなことはこだわらないようにしないと、寿命がどんどん縮まりますから。
言いたいことはいっぱいありますよ。Flashのグラデーションカラー調整バーが右端に行くと画面の外に消えてしまって触れなくなることや、たくさんのファイルを開いていると、そのファイルの切り替えボタンにマウスが乗るたびにファイル名がポップアップされるのは、なんすか? 必要ないでしょう。
そこにファイル名が書かれているのに、なんでポップアップするんのでしょ。しかもそいつが邪魔でマウスクリックが反映されなし……あぁーん。どないなっとんねん!
だいぶ、溜まっているようなので、ここらで───。
小さいことは気にしないのです・・・ ( ̄ω ̄;) ホンマカイナ...
2014年 11月23日(日)19.0℃(午後 5時50分)
連休ですが……それが?
土曜日から始めたAE(アドビのAfter Effects)の合間に、秋の山へ行ってきました。パソコンばかりにしがみ付いているワタシではないのです。たまーには外出もします。めったにないことなので、散々ここで自慢して行きます。

山は燃えていました
紅葉がちょうどいい具合で、真っ赤に燃えておりました。場所は西宮文学全集でお馴染みの、酔っぱらって、適当な最終バスに乗っていたら、ここで降ろされた、というお寺です。北夙川地区では有名なお寺です。
で、一夜明けて。今日はこれ三昧。
AEっす。After Effectsっす。一度嵌(は)まるとなかなか抜け出せないデザインアプリです。
今日は一度はやってみたい、パーティクルワールドです。
さて覚書です。
理由はわかりませんが、パーティクルは3Dレイヤーにするとだめです。
作り方。
レイヤー → 新規 → 平面レイヤーを作ります。
そして、 エフェクト → シミュレーション → CC particle World です。
以下は自分でやってみて理解できたパラメーターです。ほとんど感想みたいなものですので当てになりません。参考程度にしてください。
Birth Rate=発生数
Longevity(sec)=寿命
physics → Velocity=散らばり具合
physics → Gravity=Gravity Vectorのさらに強さ
Gravity → Vector=その軸の重力値
particle Trancefer mode=Addにするとキラキラする
サンプルムービーでは、宇宙を飛んでいる彗星を後ろから追いかけて、ぐるっと先頭に回り込んで、頭から突っ込んで終わっています。
この回転する動きも、ヌルオブジェクトを親にするカメラレイヤーを作り、動かしているのはヌルオブジェクトのほうです。
ぐるっと回転しているのは、Y軸に回転させているからです。
ヌルオブジェクトを選択しておいて、トップビューを見ながらやるとイメージがつきやすいです。
昔、このパーティクルをFlashでやって、頭を爆発させていた頃が懐かしいです。
頭が爆発するのは、たいして変わりませんが………。
2014年 11月24日(月)20.0℃(午後 12時40分)
連休ですが……はて?
休日はPCにかじりつくに限りますね。
ワタシの場合、ずっとかじりついたままですが………。
で、今日は──。
これから多く使うであろう、いやこれまでFlashで四苦八苦していたパーティクルの続きです。
あの苦労が超簡単にできる、という喜びに、小躍りどころか、独りフォークダンスでも披露したい気分になっています。
大阪弁ではこういう人のことを、『うれしガリ』と呼んで、大勢から囃し立てられます。
でも、嬉しいんですから仕方がありません。
Flashの時はあの光の粒一つ一つを手で配置して、モーションガイドレイヤーでカーブを描くように作っていたんですよ。しかも動きはギクシャクします。Flashの構造なのでしょうね。ゆっくりと動くオブジェクトの移動はとてもスムーズとは言えませんでした。
で、うれしガリは、CC Particle SystemsⅡ というのを選んでみました。
昨日の CC particle Worldとどう違うのか。
結果を先に書きますと、なんも変わりませんでした。SystemsⅡのほうが、いくつかパラメーターが端折られていて、簡素になっているだけのような気がします。
さて覚書です。
円弧を描くような動きですが──。
Producer → Position パラメーターをタイムラインに沿ってキーフレームを打って変更してますが、パーティクルエフェクトを施した、平面レイヤーをWクックして編集モードに入ると、モーションガイドが表示されて山なりの綺麗な曲線を簡単に描くことができます。
このパーティクルは、デフォルトのままだと派手すぎますので、
Birth Rate=0.2
Longevity=1sec
Producer → Radius X=3
Producer → Radius Y=23
ふわりとさせたいので、
physics → Velocity=0.1
physics → Gravity=0.1
としてみました。
さて、うれしガリはここまでです。
AEで拵えている映像は、最終的にPremiere(以降PRと書きます)に配置されて、ほかの映像と合成して書き出さなくてはいけません。そこで、このキラキラ映像をaviファイルに書き出して、PRで読み込んで他の画像と合わせてみることにしました。
うれしガリ野郎が一気に真っ青です。そうです。キラキラ映像の黒背景も一緒にデータ化されるので、PRに乗せてある別の映像を覆い潰してキラキラは見えますが、他の映像が見えません。
これは当然と言えば当然で、キラキラの映像は黒背景も含めて一つのものだからですね。
次にSWFで書き出してみましたがキラキラも無くて真っ黒け。
それなら、AEのプロジェクトファイルをそのままPRで読み込んでみようとしましたが、『カメラフィルターが設定されていません』というエラーと共に拒否されました。
念願のキラキラができても、これでは使いものにならないです。
おいおい。天下のアドビさんがこんな片手落ちみたいなことはせんじゃろ? と言う気分で、かつ、ちょっち焦り気味にネットを彷徨いました。
ようやくAdobeのヘルプでAEとPRの連携という記序を見つけて、一安心。以下の方法で無事キラキラ映像がアルファー処理を施されて合成することができました。
1)PR側で、ファイル → Adobe Dynamic Link → After Effect コンポジションを読み込みとする。
2)AEのプロジェクトが入っている場所を選び、コンポを選択。
3)シーケンスのトラックに配置。アルファーなども正しく表示される。
以下のサンプルは、以前作っているテスト的な映像にキラキラを合成しています。映像自体には意味はありません。単なる実験用です。
今悩んでいるのはこのパーティクルを止める方法が分かりません。
今回はフェードアウトさせていますが、何か方法があるのではと探っているところです。
それとPR側の悩みが一つ解決しました。
一度プロジェクトでシーケンスを設定してしまうと、例えばビデオサイズ、1920×1080だったところを800×600などに変更できないという問題です。
ファイル → 新規 → シーケンス
とやり、新しいシーケンスを拵えます。その時にシーケンス設定が出ますので、そこで800×600とかに変更したシーケンスを作成。
旧シーケンスに載っていた全てのクリップをコピーして新規シーケンスに貼り付けたらうまくいきました。
旧シーケンスは削除もできます。
2014年 11月25日(火)18.0℃(午前 7時10分)
連休も明けて……
今年最後の連休も終わりました。有終の美を飾ったような晴れ続きの連休でしたが、一転して今日は雨です。これで冬に突入するのでしょうか。そして12月に入ればあっというまにお正月です。
さて、季節と天候は移り変わっていきますが、こっちのやっていることは何も変わりません。AE のエフェクトを端から試してマスターしていくこと、今年はこのまま暮れていくことでしょう。
で、まずは Light Burstです。
簡単に言うと後ろから強い光を当てたように見せるエフェクトです。それを左右に振れるのが、Photoshopとは違うところです。
用途が異なるので比較するもんではありませんが……。
昔、Flashをメインでやっていたころ、Photoshopの描画技術で動的に動かせたらどんなにすごいかと思って、レイヤースタイルの数値を10%刻みにして16枚のjpgに分解、それをFlash上でマウスが乗ったら動き出すというのを作ったことがあります。それがこのサイトの天辺で動いているコンテンツボタンです。
とうことはAEで作ったムービーをFlashに載せれば、マウスの動きに合わせて動くようなインタラクティブ的なものも作れるということです……か?
これで来年のテーマが決まりました。FlashとAEの連携です。
さて覚書です。
まずテキストレイヤーを作り、文字を入れます。
そのテキストレイヤーをCtrl+Dでコピーして同じ場所の前面に貼り付け、レイヤー → レイヤースタイル → べベルとエンボスを掛けて少し立体的な文字にしました。
背面のテキストレイヤーに、Light Burstを掛けます。
エフェクト → 描画 → CC Light Burst 2.5 を選択です。
そのままだと黄色い光なので、もひとつ、色調補正 → 他のカラーへ変更というエフェクトを取り入れて、ライム色の光に変えています。
ついでにLight Burstが掛けられたテキストレイヤーの背面でレンズフレア → レンズの種類105mm、でLight Burstの動きに合わせて、左右に振っています。
前回のパーティクルですが、エフェクトの中には「パーティクルプレイグラウンド」というのもあるのですが、こっちはなんなんでしょう?
今度試してみようかと思っていますが──それにしても、あり得ないほどのエフェクトがまだまだ待ち受けています。
恐るべし、After Effects ・・・( ̄  ̄;) うーん
<


Copyright(C) 2004 D-Space Keyoss.
All rights reserved.